マイグレーションの種類や流れを詳しく解説!成功のポイントも
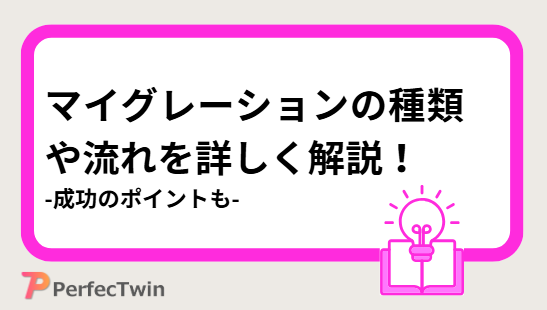
システムの老朽化やクラウドへの対応が求められる中で、「マイグレーション」という言葉を耳にする機会が増えています。
しかし、「そもそもマイグレーションの意味とは?」「どんな手法や種類があるのか」「リプレースとの違いは?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、マイグレーションの基本的な考え方から、代表的な種類や手法、そして導入によって得られるメリットまでをわかりやすく解説します。
あわせて、マイグレーションを円滑に進めるための成功のポイントも紹介しますので、移行を検討されている方はぜひ参考になさってください。

テスト自動化ツール「PerfecTwin」
- ✔テストケース作成が不要
- ✔機能テスト・性能テストを自動化できる
- ✔世界6か国で特許出願完了
マイグレーションとは?
マイグレーションとは、ITシステムやデータを現在の環境から別の環境へ移すことを意味します。
ここではその基本的な意味と重要性を、3つの観点から分かりやすく解説します。
マイグレーションの定義と重要性
マイグレーションの重要性は、コスト削減やセキュリティ強化、システムの安定性向上といった点にあり、企業の成長戦略に直結する取り組みと言えるでしょう。たとえば、ホストコンピュータの保守切れを契機に、オープン系のサーバーシステムへの移行を検討する企業も増えています。
こうした背景を踏まえてマイグレーションを理解するには、規模や目的に応じた3つの知識「データ」「アプリケーション」「インフラ」の視点で整理して考えることが有効です。
マイグレーションと関連用語の違い
マイグレーションと似た用語には、アップグレード、コンバージョン、リプレースなどがあり、それぞれ意味が異なります。
たとえば、アップグレードは同じ製品内での機能向上を指し、コンバージョンはデータ形式の変換、リプレースはシステムそのものを入れ替える行為です。
これらの用語は段階や流れに応じて使い分けられるべきであり、IT用語として混同されがちですが、目的や影響範囲が異なります。
マイグレーションは、これらすべてのプロセスを内包しうる広義の概念である点が特徴です。さまざまな用語の違いを正確に理解することで、より適切なIT戦略の立案につながります。
マイグレーションの目的
マイグレーションは、単なるシステムの移行ではなく、老朽化した環境から脱却し、効率性・安全性を高めるための重要な取り組みです。
以下に、その目的と背景を詳しく解説します。
システムの老朽化対策
基幹システムを長期間使い続けると、機器やソフトウェアの老朽化が進み、障害リスクや保守コストが増加します。古いシステムのままでは最新の技術を取り入れることが難しくなり、業務効率にも影響が出ます。
そのため、定期的なメンテナンスとともに、計画的な更新が不可欠です。老朽化した機器を維持し続けるのではなく、新たな技術への移行という手段を検討することが、継続的な運用の鍵となります。
保守終了を契機としたマイグレーションの必要性
マイグレーションの背景には、ホストコンピュータの製造終了や保守サービスの打ち切り、あるいは業務パッケージソフトのサポート終了といった外的要因がある場合も少なくありません。
これらの終了時期が迫ることで、企業はシステム移行の判断を迫られます。
特に、代替機器や部品の調達が難しくなることで、障害対応が困難になるリスクも高まります。こうした状況では、移行を計画的に進めることが事業継続の観点からも極めて重要となります。
コスト削減と効率化
企業がマイグレーションを検討する一つの大きな理由は、コスト削減と業務の効率化にあります。
特に古いシステムの保守にかかるコストは年々増加する傾向があり、更新によってその負担を軽減することが可能です。
システムを最適な形に再構築することで、運用管理もやすくなり、業務全体の効率が向上します。保守費用の削減や再配置されたリソースの活用など、企業全体にとって実用的で使える改善効果が期待できます。
セキュリティ向上の必要性
セキュリティリスクが高まる現代において、老朽化したシステムでは十分な対策を講じるのが難しくなります。
マイグレーションは、こうしたセキュリティ課題の改善を進める上でも有効な手段です。
最新の環境へ移行することで、正確で適切なアクセス制御や脆弱性対応が可能となり、安全性の確保につながります。
企業ごとのニーズに応じた解決策を導入することが、信頼性の高いシステム運用には不可欠です。
マイグレーションの種類
マイグレーションにはさまざまな形態があり、目的や対象システムに応じた対応が求められます。
ここでは代表的な4つのマイグレーションの種類について、それぞれの特徴と注意点を紹介します。
データマイグレーション
データマイグレーションとは、既存のシステムから新しい環境へデータを移行するプロセスです。
目的を明確にし、変更やコンバージョンには最新の技術を活用することで、効率的かつ正確な移行が可能になります。
特に注意すべきなのが文字コードの違いやデータベース構造の不一致です。これらを見落とすと、移行後に文字化けや参照エラーといった問題が発生する可能性があります。
資料や過去のケースを参考に、データの変化に柔軟に対応できる体制を整え、アップデートされた環境での安定運用を目指しましょう。
サーバーマイグレーション
サーバーマイグレーションでは、オンプレミス環境からクラウドへの移行、あるいはサーバーの再構築が対象となります。
まず、オンプレミスとクラウドの違いを理解し、自社にとって最適な運用モデルを選ぶことが重要です。
仮想マシンの管理方法やOSの移行方法を把握したうえで、作業手順を整理し、チェックリストを作成することで、移行中のトラブルを防ぐことができます。検索・呼び出し機能など、利用者の利便性も考慮した設計が求められます。
クラウドマイグレーション
クラウドマイグレーションは、既存のアプリケーションやシステムをクラウドプラットフォームへ移行するプロジェクトです。
まずは、アプリケーションの依存関係を正確に把握し、移行可能な構成を確認することが大切です。
次に、手順を具体的に計画し、必要なインフラ環境や容量を見積もることで、無駄のないスムーズな移行が実現します。
加えて注意すべきなのが、個人情報や機微情報をクラウドに移すことへの顧客の抵抗感です。特に金融や医療などの業界では、データ保護や法令遵守(コンプライアンス)に対する信頼性が求められます。
クラウド上での暗号化・アクセス制御・監査ログの整備など、十分なセキュリティ対策を講じ、安心して移行できる環境を整えることが、プロジェクト成功のカギを握ります。
レガシーマイグレーション
レガシーマイグレーションとは、技術的に古くなった既存のシステム環境を、新しいプラットフォームや最新の技術基盤へと移行するプロセスを指します。
移行には、プログラムの再構築やデータ形式の変換、動作環境の変更など、技術的な対応が複合的に求められることがあります。
特に、レガシーシステムは独自仕様で構築されている場合が多く、安定した移行を実現するためには、入念な計画が不可欠です。事前のバックアップ取得、設定の確認、バージョン管理の徹底といったステップを段階的に進めることで、リスクを抑えたスムーズな移行が可能となります。
マイグレーションの手法
マイグレーションには目的や対象システムに応じて複数の手法があります。
ここでは代表的な4つの手法について、それぞれの特徴や実施上のポイント、検証方法とその難易度を解説します。
リホスト(リホスティング)
リホストは、既存のシステムを大きく変更せずに、新しいサーバーやOS環境へ移行する方法です。
対象となるのは、基幹業務を支えるシステムなど、停止が許されない業務環境です。
リホストのメリットは、短期間での移行が可能で、コストを抑えやすい点にあります。
一方、ライブ環境での移行にはリスクも伴い、対象システムの特徴に応じた慎重な判断が必要です。該当範囲を事前に明確にし、期待できる効果を含めて移行を検討しましょう。
リホストでは、基本的に「現行環境との動作比較テスト」が中心です。
バッチ処理や帳票出力の結果が旧環境と一致するかを検証します。
アプリケーションロジックを変更しないため、テストの難易度は比較的低く、項目も限定的です。ただし、ミドルウェアの互換性や接続先機器の動作検証は必要です。
リライト(リライティング)
リライトとは、既存のコードや仕様を活かしつつ、新しい技術やプラットフォームに適合するよう書き直す手法です。
たとえば古いIT資産を整理し、現在の環境に合った仮想化やクラウド対応に適応させる場面で用いられます。リライトには一定の時間と労力がかかりますが、元の設計思想を残しながら機能をアップデートできるのが特徴です。
気軽に始めるのではなく、洗い出しや回避すべきポイントを事前に整理することが成功の鍵です。
リライトでは、「機能単位の結合テスト」と「回帰テスト」が中心になります。
コードが書き直されるため、単体テストだけでなく、既存機能が正しく再現されているかを総合的に検証する必要があります。
難易度は中程度~高めで、業務フローを熟知したテスト設計が重要です。
リビルド(再構築)
リビルドは、既存のシステムを一から新しく開発・構築し直す手法です。
老朽化したアーキテクチャや運用負荷の高い構造を根本から見直すことで、強化された新しい構造を実現できます。
リビルドのプロセスでは、現行機能の整理、新たな機能の設計、テストを含む一連の工程を経て、より柔軟で拡張性の高いシステムを作成します。将来の拡張や変化への対応を見据えた選択肢として、戦略的なマイグレーション手法と言えます。
リビルドでは、「要件ベースの新規テスト計画」が必要です。
既存システムとの比較に加え、追加・変更された機能も新規に検証します。
単体・結合・システム・ユーザーテストまでフルスコープで対応するため、テストの難易度は非常に高いです。
プロジェクト初期からの綿密なテスト設計が不可欠です。
リファクタリング(再設計)
リファクタリングは、ソフトウェアの内部構造や設計を見直し、より効率的で保守性の高い形へ再設計する手法です。
コードの一部を整理・置き換えることで、全体の品質を向上させつつ、外部から見た動作仕様は保たれます。
たとえば、古い製品で使われていたロジックを、モダンな設計パターンに置き換えることで、今後のリプレイスや機能追加が容易になります。
設計の種類や目的を明確にし、入れ替えに伴う影響を見極めることが重要です。
リファクタリングでは、「ユニットテストの自動化」が重要な手法になります。 外部仕様を変えない前提のため、既存のテストケースをベースに正確な結果が得られているかを確認します。 難易度は中程度ですが、既存テスト資産がない場合は、事前にテストコードを整備する必要があります。
このように、マイグレーション手法ごとにテスト戦略と負荷が異なるため、選定時には検証工数や体制も含めて総合的に評価することが成功のポイントです。
マイグレーションの流れ
マイグレーションを成功させるためには、現行システムの評価から本番移行までの各工程を段階的かつ戦略的に進めることが求められます。
本章では、全体の流れを順を追って解説します。
現行システムの評価
まず最初に行うべきは、現在稼働しているシステムの状態を詳細に分析することです。
既存システムの技術的課題や運用上の制約といったデメリットを洗い出し、新システムとのギャップを明確にする必要があります。
そのうえで、ターゲットとする新システムへの移行が、技術面だけでなく、コストや期間の面でも実現可能であるかどうかを多角的に検証します。
このフィージビリティの検討は、移行計画全体の現実性を左右するため非常に重要です。
また、評価が主観的にならないよう、必要に応じて外部の専門家や第三者による客観的な評価を取り入れることで、より信頼性の高い判断が可能になります。
こうした慎重な評価を怠ると、移行計画が「絵に描いた餅」に終わるリスクがあるため、初期段階での精緻な分析が求められます。
テストとリハーサル
テスト工程では、移行の成否を左右する重要な要素を多く含んでいます。
まず、テストカバレッジをどの範囲まで担保するのかを、要件定義の段階で明確にしておくことが不可欠です。
また、現行システムと新システムでの結果を効率的に比較検証できる仕組みを設けるとともに、性能検証では現実に即したトランザクションミックスや過負荷シナリオを想定してテストを行う必要があります。
さらに、移行リハーサルを実施する際には、現行の本番環境に影響を与える可能性があるため、万が一の障害を引き起こさないよう細心の注意を払う必要があります。
本番移行
本番移行では、移行手順の最終確認と万全な体制構築が求められます。
特に、コードフリーズ期間中は、ビジネスに支障が出ないよう、事前にビジネス部門との合意を得ておくことが重要です。
また、新システムで障害が発生した際の対応方針についても、想定される障害の重要度ごとにシナリオを準備し、切り戻しの判断基準や対応手順を明文化しておく必要があります。
これにより、有事の際にも迅速かつ的確に対応できる体制を構築することができます。
マイグレーションの成功のためのポイント
マイグレーションを成功させるには、計画的な準備と組織的な連携が不可欠です。
以下では、成功に導くための重要な視点を解説します。
徹底した準備と計画
マイグレーションを円滑に実施するためには、まず目的を明確にすることが不可欠です。
目的に基づいて全体の構成を把握し、それに沿って処理の流れを設計する必要があります。また、事前に詳細な準備を行い、必要なリソースや環境を完全に用意しておくことで、移行時のトラブルを最小限に抑えることができます。
準備の精度が、移行の実現度に大きく関わってくるといえるでしょう。
関係者への周知とサポート
マイグレーションでは、関係者との連携と周知が成功の鍵を握ります。
まず重要なのは、ビジネス側に対して、マイグレーションを実施する目的や背景を明確に伝え、それにより得られるビジネス上のメリットを丁寧に説明することです。これにより、マイグレーションを情シス部門だけの課題とせず、全社的な課題としてとらえてもらい、必要な協力を得やすくなります。
また、関係者に関連する情報を適切に提供し、どのような機能やサポートが用意されているのかを明確にすることも重要です。
あわせて、相談窓口を設けて疑問や不安に対応することで、関係者の理解と支援をさらに深めることができます。
外部サービスの活用
マイグレーションを効率的に進めるには、自社のリソースを見直し、必要に応じて外部サービスの利用を検討しましょう。
とくに、SaaSなどのクラウドサービスを活用することで、ネットワーク構成の簡素化や運用負荷の軽減が可能となります。
適切な外部サービスを使うことで、移行に必要な機能を効果的に用い、全体のプロセスをスムーズに進行させることができます。
マイグレーションにおけるリスクと課題
マイグレーションでは、技術や人的リソース、ドキュメントなど、さまざまなリスクと課題に対応する必要があります。事前の備えが成功の鍵となります。
技術的な課題
マイグレーションに伴い、新たなプラットフォームへの対応には技術的な困難が伴います。
特に業務に必要な技術が新しい場合、その技術に関して他社での適用事例があるかを確認することが重要です。
事例がない場合は、PoC(概念実証)を通じて事前に技術の適用可否を評価し、第三者によるレビューを受けることが望まれます。
また、問題発生時のトラブルに備えてチェックポイントを設定し、バックアッププランを準備することで、移行中の技術的リスクを最小限に抑えることができます。
人的リソースの不足
マイグレーション作業、とくにレガシーシステムの移行では、必要なスキルを持つ技術者の不足が大きな課題です。
まず現状のリソース体制を把握し、作業負担の偏りを見える化することが重要です。
その上で、外部の専門リソースの活用も視野に入れつつ、移行ツールやテストツールを取り入れて手間を軽減する工夫が求められます。
こうした取り組みにより、限られたリソースでも確実に作業を進める体制が構築できます。
ドキュメント不足の影響
移行対象のシステムに関するドキュメントが不足している場合、マイグレーション全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
ドキュメントの形式を統一し、不足部分を整理するだけでなく、リバースエンジニアリングツールなどを用いてソースコードから仕様情報を抽出することも有効です。
また、過去の不具合や事例を共有・蓄積しておくことで、複数の関係者間での情報伝達がスムーズになり、将来的なトラブルの抑制にもつながります。
まとめ
マイグレーションは、業務効率やシステムの安定性向上など多くの利点をもたらす重要な取り組みです。
導入のポイントや注意点を踏まえ、成功事例を参考にしながら進めましょう。
マイグレーションの重要性の再確認
マイグレーションを導入することで、旧システムをそのまま使い続ける場合に比べて、保守コストや障害リスクを大きく低減できます。
実際に、大規模システムを新環境へ切り替えることで、パフォーマンス向上や運用効率の改善を実現した導入事例も多く存在します。
移行時には、データの整合性確保やシステム停止の影響など、注意すべきポイントがいくつかあります。
これらを整理し、計画的に進めることが成功への鍵となります。
今後の展望と戦略
今後、マイグレーションは単なる技術的更新にとどまらず、ビジネス全体の向上を支える基盤として重要な役割を担います。
クラウド化やDXの進展に伴い、マイグレーションの可能性はさらに広がっていくでしょう。
事業戦略においても、継続的な最適化やセキュリティ強化に向けた取り組みとして位置付けられています。
今後の展望を踏まえたうえで、「目的に応じた段階的移行」「終了期限を見据えた計画」「柔軟な運用設計」など、具体的な指針を一覧化し、自社に適した戦略を構築することが求められます。

テスト自動化ツール「PerfecTwin」
- ✔テストケース作成が不要
- ✔機能テスト・性能テストを自動化できる
- ✔世界6か国で特許出願完了
